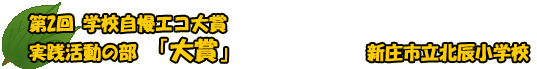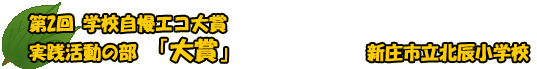|
■ タイトル
広がれ けやきプロジェクト
山形県新庄市立北辰小学校
 ■ 目的
校庭には、樹齢300年余りのシンボルの大けやきを中心とするけやきの森、もみの木、イタヤカエデなど50種類もの樹木がある。また、絶滅が危惧されている天然記念物のイバラトミヨが学校のすぐそばを流れる指首野川や、周辺の小川に生息している。これらの自然と関わりながら、自分たちのふるさとを誇りに思い、地域に生きる「もの・人」を思いやる気持ちを育て、循環型社会の中で生きていく行動力を身につけることを目指していく。
■ 活動
全学年の環境に関わる課題を発見し、自分たちでできることは何かを考え実践し3年目になる。そこで、これまでの実践をふまえ柱を2つ立て、全学年で取り組んできた。
1.地域環境から学ぶ
昨年までは6年生が、イバラトミヨの生態と取り巻く環境を調べ、これまでの学習を新聞にまとめて発信してきた。今年は4年生が引き継ぎ活動の主体となり、保全指導員や県農村整備課職員や地域の方々と連携しながら、児童の「守りたい・増やしたい」という思いが叶えられるように進めてきた。そのため実際に、イバラトミヨの巣作りを観察したり卵を孵化させて稚魚を放流したり、イバラトミヨの保全池や看板を作ったり、発信したりなどしてきた。6年生は「未来に残したい新庄」のパンフレットを作成し、これまでの実践を他地域(仙台駅)でも発信するなど、環境保全の輪を広げる活動をしてきた。
2.エネルギーから学ぶ
自然環境をフィールドとした活動を支えるために、全校児童で校庭の落ち葉を集め、バイオマスセンターの協力を得ながらたい肥作りを行った。それを活用し、米や野菜や花を育て、バイオマスエネルギーや日光のエネルギーは、自分たちの活動エネルギーとなることを実感した。また、1年生から身近な風・雨・太陽などの自然エネルギーについて諸活動を通して体感するなど、各学年のエネルギー学習が感動的な活動となった。それがPTAの「100万人のキャンドルナイト」や「夏の省エネ10ポイント」の参加に広がっていった。
■ 成果
校庭のけやきの森からスタートした学習は、指首野川へ広がり、「イバラトミヨ」に出会い、その生態調査、川の水質検査、さらに保護活動へと広がりをみせていった。それらが6年生から4年生へ引き継がれていき、本校の新たな伝統となった。保護活動や様々な方法での発信活動により、家庭や地域においてもイバラトミヨの関心が高まってきた。各学年のエネルギー学習では、エネルギーを身近に感じるようになり、省エネやリサイクルなどの活動について考え実行できるようになってきた。
子どもたちは、3年間の学習を通して自分のふるさとの宝物を発見し、大切にしようとする気持ちが育まれた。自分の生活を振り返り、身近な環境を見つめ直し、生き物(命)を大切にしようとする環境保全の意識も高まった。多くの人々との交流や関係も生まれ、積極的に地域の学習会に参加したり、主体的に行動できるようになったのは、大きな成果である。さらに、保護者も子どもと共に学び続け、PTA広報誌を通して互いに紹介しあったり地域へ働きかけたりし、環境保全の意識が高まっていったことも成果の一つである。

 |
 |
↑秋の恒例行事となった、秋のクリーン作戦。
10〜11月は、何度も落ち葉集めをします。休み時間に何度も集めました。
←樹齢300年余りのけやきの森 |
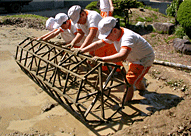 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5年生は、落ち葉の堆肥で無農薬の米作りに挑戦。昔ながらの手作業です。 |
 |
指首野川の水生生物調査・イバラトミヨ捕獲にチャレンジ。 |
 |
イバラトミヨの巣と卵。当番を決めて、巣作りの様子やふ化する様子を観察し、記録しました。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| イバラトミヨの生息地の水質調査。 |
 |
イバラトミヨの保全池に救出した魚を入れる。 |
 |
指首野川にふ化させた稚魚を放流。 |
|